よく私たち世代より上の人たちは「子どもを叩くのは躾のひとつ」だったと思います。子どもが悪いことしたら叩く、叩くことで親の言うことを聞かせる。これが当たり前だったのではないかと思います。しかし、今は「親権者等は、児童のしつけに際して、体罰を加えてはならない」となっています。
私たちが子どもの頃は体罰は当たり前だった
私たちが子どもの頃、親や先生から体罰されるのは当たり前ではなかったですか?悪いことをしたら玄関で正座したり家に入れてもらえずに庭に出されたり、学校では教材や宿題を忘れたら髪の毛引っ張られたり…といったことは日常的にありました。今はそのようなことはあってはならないのですが、「自分もそう育てられたから、自分もそうやって育てます」という現役子育て世代の人はいらっしゃいます。
叩くことってダメなの?
叩くことがダメというのは、今の世間ではよく知れ渡っていると思います。叩くことがダメであるというのは、保護者の方も理解されている方は多い一方で、「自分もそうやって叩かれてしつけされてきたので、わが子にもそうします」と宣言される方もいます。叩くことがダメであることは、こちらの記事に詳しく書いていますが、「叩いてしつけをする」ということは、根本的な解決にはなりません。

「親が怖いから、親に叩かれていたいから、〇〇をしない」という考え方になります。実際叩いたところで、その一回でいうことを聞くかというと、そうではないと思います。叩くことで子どもの脳にダメージを負わせるだけでなく、保護者も人間なのでだんだんヒートアップして行って、叩くことがエスカレートしていき、更に子どもを身体的に傷つけてしまう可能性があります。誰も子どもを傷つけたいなんて思ってはいないけれど、そうせざる得ない保護者の心までも傷つけてしまいます。
怒鳴ることってダメなの?
叩くこと以外にも、最近は感情的に怒鳴ることも子どもの脳にはよくないと言われています。ずっと怒鳴らずに過ごせる保護者なんている?普通に怒鳴ることなんてよくあるじゃない?と思う方が多いと思います。私もそう思っていました。ただ、やはり怒鳴るという行為は、子どもの脳を傷つけるということがわかっており、避けた方がいい行為だと言われています。私自身も数年前までは年に何回か、子どもを怒鳴ることがありました。いうこと聞かない子どもたちに対して、「いい加減にしてって言ってるじゃない!」と感情的に怒鳴っていました。怒鳴ることに対して子どもが「ママ大きな声出さないで~」と泣き出すのを見ると、申し訳なく思う気持ちと、だったらダメって言ったときにいうこと聞いてよ、と思いながら過ごしていました。もちろんヒートアップしていた気持ちが下がったときには「そこまで怒らなくて良かったよね…。」と反省する気持ちが出てきて、子どもに対して怒鳴ったことを謝罪していました。
そんな中、怒鳴ることをやめたきっかけは、こちらのホームページを見た時でした。
怒鳴ることでさえも、子どもの脳には影響して、子どもが大きくなった時のメンタル面などに大きく影響してきます。私は子どもの頃、父の怒鳴る声を聞きながら育ちました。それもあってか、人の顔色をうかがったり、職場で怒鳴られる声を聞くと、ものすごく嫌な気持ちになって自分の精神状態にも影響してきます。私はそれと同じことを自分の子どもにしてしまっているのだなということに気付き、やめました。
ただ、「子どもに悪影響があるからやめよう」とその瞬間からやめるのは、非常に難しいと思います。毎日怒鳴っている保護者がある日をきっかけに怒鳴ることをゼロにするのは、とても忍耐力が要りますし、非常に難しいことかと思います。忙しい生活の中で自分の感情をコントロールするのは大変なので、少しずつ怒鳴る頻度を少なくしてゼロにしていくというイメージで、試してほしいと思います。
怒鳴る・叩く気持ちはとてもわかる
育児をしていると、怒鳴ってしまったり叩いてしまったりする気持ちは、とてもよくわかります。そもそも保護者も感情を持った人間ですし、家事・育児をこなし、自分のことは後回しで時間がない中、人間関係でイライラすることもあると思います。なのでイライラしたり怒ったりしてしまうのは当然だと思います。女性だと、ホルモンのバランスの崩れでイライラしやすくなったりします。そんな保護者に対して保健師がただ「怒鳴ったり叩いたりするのはやめましょうね」と淡々と言ったところで、「そうですね」と保護者が受け取ることは難しいと思います。「じゃぁ自分は子育ての中で叩いたことも怒鳴ったことも一回もないの??」「こっちの育児大変わかる??」と保護者は思うと思います。
私自身も一度だけ叩いたことはある
まだまだ子どもが小さかったころ、月に1回ほど大爆発して子どもを怒る時期がありました。病院帰りに車の中で泣き叫ぶ二人に「静かにしてよー!」と自分も泣いていました。上の子は叩いたことがないのに、一度だけ、下の子の足を叩いてしまったことがあります。外食時に下の子が何度も土足の足を机に置くので、無意識にポンと軽く叩いてしまいました。無意識に叩いてしまったことは、本当に自分でもびっくりして、物凄く罪悪感に襲われ、保育園の先生にしんどくて話を聞いてもらったことがあります。なので、叩いてしまう・怒鳴ってしまう保護者の気持ちはよくわかります。
『マルトリートメント』を知って私自身も考え方が変わった
少し前までは「怒鳴る」ということに対しては、これだけ育児しんどかったら、どの家庭でもあるよね…とは思いながら仕事をしていました。ただ、自分で勉強していた時にこの『マルトリートメント』という言葉を知り、子どもの脳に影響が出てしまうということが分かった以上、やはり怒鳴ることはダメだと思いました。そいういえば昔、私の育った家庭では、父親の怒鳴り声がよく響いてました。そのような環境で育ったためか、ものすごく人の顔色をうかがったり、職場で怒鳴り声がすると思考が停止するときがあります。そのような事を自分がしているのだと反省し、やめました。
ただ、「じゃぁダメだから今からやめます」というのは、叩く・怒鳴る頻度が高く、何の解決策もないままだと、結構難しいと思います。
自分で自分の感情をできるだけコントロールする
イライラしてしまう・怒鳴ってしまう・叩いてしまう…と話をしてくれる保護者に対して、どうしたら怒鳴ったり叩いたりせずに過ごせるかという話をするのですが、それらを防ぐためによく伝えるのが、
- イライラする時や感情が爆発する時は「一番頑張っているとき」と自分をほめる
- 「保護者は家事も育児もやって当たり前」というように思われているけれど、当たり前ではない
- イライラして子どもに声をかける前に自分の好きなお菓子をストックしておいて、それを一つ食べる
- どうしても怒りが収まらないときは安全を確認して子どもと距離を作り、時間を決めてトイレにこもってSNSしたり音楽聞いたり本を読む
というように自分の感情をコントロールすることです。そして大事なのが、
「ピタッとやめるというよりも、怒鳴る・叩く回数を少しずつ減らしていく」というイメージを持ってもらうことです。
すっと怒鳴る・叩くことをやめれたらいいのですが、今までしていた習慣をいきなりやめるのは、保護者にとってもストレスになり、そのストレスが溜まって悪循環になるかもしれません。なので怒ってしまいそうになった時はマルトリートメントを思い出して自分の怒りを鎮める方法をとる。それができずに怒鳴ってしまったとき、恐らく保護者は後になって一人反省会をするのではないかと思います。怒鳴ってしまったときは、子どもに「大きい声で怒ってしまってごめんね」と言って子ども抱きしめたら、もう自責の念は捨てて「次はやめる」と前を向いて過ごしてほしいと思います。
マルトリートメントを知ってから、感情のコントロールをできるように対処してみた
子どもは4歳くらいになると、「頑張る」「我慢する」という自制心が出てきて、聞き分けはよくなってくると思います。それでも、まだ子どもなのできょうだい喧嘩や気持ちの切り替えが上手くいかずにかんしゃくを起こすこともあります。なので私はマルトリートメントを知ってからは自分の感情をコントロールするために、
- 仕事が終わって帰宅した夕方の時間は空腹でイライラしないように先にご飯をつまみながら子どもたちをお風呂に入れる
- 昔読んでいた好きな漫画を実家から持ってきて短時間読む
- SNSで愚痴を言えるアカウントを作ってストレス発散をする
- 子どもの安全を確認してトイレに引きこもる
- 我慢できないとき用に好きなお酒を用意する
- ワイヤレスイヤホンを片耳につけて好きな音楽を聴く
という対処法を取るようにしました。
『ドイツ流 絶対に怒らない子育て』の本と、伊藤忠の『子どもの視点』は子どもの事がよくわかって、ちょっと意識が変わった
ある時、図書館でたまたま手に取ったこの『ドイツ流 絶対に怒らない子育て』という本が、育児をする上でとても参考になりました。子どもの成長段階の事や、どうして親と子どもがぶつかってしまうのかなどといったことが、わかりやすく書いてあり、子どもの気持ちを理解しやすい本になっています。
子どもの困りごとに関してはどの国でも同じなのだなと思えます。「子どもが親を困らせている」という表現をされることがありますが、実は違って、それは子どもの成長発達の段階で、こういう理由があるからそういう状況になっているといったようなことが色々書かれています。
子どもの成長段階を知らないと、なぜ子どもがそうするのかということがわからず、スムーズに子どもが物事を進めないことに関して怒ってしまったりするので、まずは子どもに関する理解が重要なんだなと、この本を読んでしみじみと感じました。結構ボリュームがあるので、すべて読むのには根気が必要かもしれないですが、とてもおススメの本になります。目次をパラパラ見て、自分がちょうど子どもとの関りで困っている箇所があれば、見てみるのもありかと思います。
また、子どもを理解するのに、実際に子どもから見た生活を実体験できる「子どもの視点」というのを伊藤忠が作っています。
「子どもの視点ラボ」という展示イベントをされていたり、東京に「子どもの視点カフェ」という子どもの視点の展示+カフェのスペースがある施設があります。

大人ではわからない、子どもにしかわからない苦悩を経験することで、子どもに対する理解が深まり、いつも怒って注意していたことも、「子どもはこうだから仕方ないよね。どうしたらうまくいくかな?」ということを一緒に考えることで、少し保護者の気持ちも落ち着くかなと思います。
昔と違って、今は核家族化になっている中で、昔とは違う子どもとの関り方を求められているので、今子育てをしてる保護者の方々は、どの年代でも大変かと思います。子どもの関り方に関しては、未就学児であれば保健センターがあり、就学以降であれば家庭児童相談の窓口が必ずどの市町村にもあるので、関わり方で困ることがあれば一度相談して客観的に見てもらうと、解決の糸口が見つかることもあります。
保護者の一人の時間は作ってほしい
保護者が一人の時間を作るのは、人によっては罪悪感を感じるかもしれません。ただ、保護者が頑張ってストレスが溜まって爆発してしまうよりも、たまに一人の時間を作ってストレスを軽減して、少しでも子どもと落ち着いた時間を過ごす方が良いかと思います。自治体によっては
- 一時預かりのクーポン券
- ベビーシッター券
- 家事代行のクーポン券
などを出産後にプレゼントしてくれている自治体もあるみたいなので、それがある自治体にある方々は是非それを使いながら一人の時間は作るようにしていただけたらと思います。
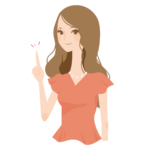
子育てのしんどさに関しては、こちらの記事も書いているので、よければ見てください。






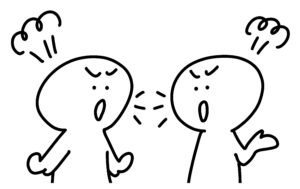
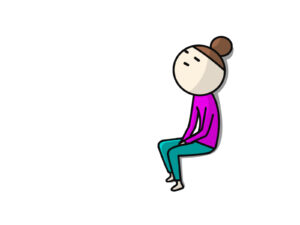



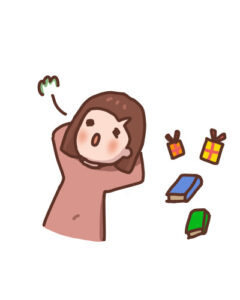

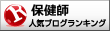
コメント