育児をしていて、「子どもを叩くことはダメ」というのはたいていの保護者の方は知っていると思います。しかし、今の保護者くらいの世代は、叩かれることはしつけとして普通だったのではないかと思います。なので叩くことはダメなの?よくあることじゃないの??と思う方もいらっしゃるのではないかと思います。
そもそも子どもを叩くのがダメな理由
子どもを叩く理由として、「言うことを聞かなくて、もうどうしようもなくて、叩いてしまいます。でも後悔しています。」という保護者の人もいれば、「うちは叩いてしつけをする家庭なので」ときっぱり言い切る保護者の方もいます。昔は「叩いてわからせる」というのがしつけの主流だったと思います。以前、私の祖母や叔母へ叩いたり怒鳴ったりすることはダメだと話をすると、「え?何言ってるの?そんなの無理でしょ。子どもなんて、手をつねったり、お尻をパシッと叩いたら、すぐ言うこと聞くわよ。今の親って大変ねぇ。」と返事されました。本当に、今の保護者の方は子育て大変だと思います。
叩いてしつけをすると、「保護者が怖いからダメなことをしない」という理解になる
子どもがダメなことをした時に、叩くとその時は言うこと聞きますよね。保護者に叩かれると痛いし怖いので、保護者のいうことを聞きます。ただ、叩くことでやめるのは恐らくその場でしか効果はないと思います。「ちょっと保護者の気を引きたいから、やってはけないことを何度もしちゃおう」「色々なことに興味があって、ついつい動いて、やってはいけないことをしてしまう。何度注意されてもしてしまう。」そういう子どものしつけに対して、「叩く」という保護者への恐怖心で子どもを支配したところで、根本的な部分(してはいけないから、しない)でやめるのではなく、「保護者が怖いからしない」という思考になります。根本的な部分(してはいけないから、しない)でやめるわけではないので、結局同じことをし、子どもは何度も注意され、保護者は何度も怒らないといけなくなり、怒鳴っても言うことを聞かないのでエスカレートして叩くことを選択してしまいます。
そして子どもは「やってはいけないことをしたら、叩かれる」という思考になるので、保育園や幼稚園などでやってはいけないことをしている子を見つけて、「やってはいけないことをしているから、叩かなきゃ」と他児を叩いてしまう可能性もあります。
恐らく今の子育て世代の親や祖母世代は、しつけとして叩かれてきた、あるいは叩いてきたと思いますが、それが子どもの脳の発達にはよくないと言われていて、避けるべき習慣だと言われています。「親が叩いてしつけしていたから、私もそうしています」と断言する方もいらっしゃいますが、結局それは負の連鎖なので、やめるべきであると思います。
「日常的にしつけで子どもを叩いていると言ったら、きっと保健師から注意されてめんどくさいだろう」という理由で、子どもを叩いていても表に出して言わない保護者の方もいると思います。叩いてしまっていること自体は良くはないことではあるのですが、私たち保健師からすると、保護者がその叩くという行動をしないといけないという背景がとても気になって、保護者のことが心配になります。だれも子どもを叩きたいと思ってそもそも子どもを産んで育てているわけではないですし、「叩かないと子どもをコントロールできない」というその状況が心配です。子どもの動きが多い、指示が入りにくい、そもそも保護者のサポートが足りていなくてイライラしているなど、そういう背景を改善していく必要があり、ただただ保護者に「叩くことはダメです」と伝えるのみでは、なんの解決策もないまま保護者が責められている状況になり、なにもプラスになりません。叩いたらダメなことぐらい、誰でもわかっていますし、子どもを叩きたい保護者なんていない、だからこそ、そこまで親が追い込まれている状況を改善していくことを目指して、どうしたら叩くまでに至らないようにできるかという話をさせてもらっています。
保健師からすると、「子どもを叩くなんて」という感じのことを思っているわけではなく、子どもを叩く行為はだれにでも起こる可能性があると思っています。私自身もそう思って過ごしていて、子どもを産む前は、自分のタイムスケジュールが乱れることがとても苦手だったので、子どもを産んで育児をしたら虐待してしまうのではないか…と思っていました。この仕事に就いていることもあり、叩くことはないのですが、5年ほど前、一度だけ、下の子に足をぺちっと叩いたことがあります。外食時に、下の子がテーブルに土足のまま足を乗っけたことがあり、その時ものすごくイラっとして、とっさに手が出てしまいました。ハッと我に返って、その後数日間は「子どもを叩いてしまった」と、とても気持ちが沈んでいました。気持ちがとてもしんどかったので保育園の先生に自分から「この間子どもの足をぺちっと叩いてしまって…」と懺悔していました。
最初はしつけでちょっと軽く叩いていたのが、だんだん回数も増えていき、叩く力も強くなって、お尻や手足を叩いていたのが頭を叩くようになって…と叩く行為はエスカレートします。その行為がもっとエスカレートしていくと、ニュースなどで流れるような虐待の事件に繋がっていくのだと思います。
叩いたところで、それ以降絶対に子どもがしてほしくないことをしないかというと、そうではないと思います。叩くことは子どものしつけにおいて、根本的な解決にはなりません。それよりも、叩かないとやめないくらい子どもが言うことを聞かない、かんしゃくが強いのであれば、それこそ心理士さんの相談に入って、どういう成長の過程で子どもが言うことを聞かないのか、言うことをなかなか聞いてくれない子どもに対してどう関わっていった方がいいのか、ということを一緒に考えさせていただけたらと思います。
自分の感情をコントロールするのは難しい
自分の感情をコントロールするのは、とても難しいです。特に育児で忙しく、疲れている中で自分の感情をコントロールするのは、とても難しいです。アンガーマネジメントで、「6秒待つ」と言われますが、私は待てる人ではなかったです…。6秒待つ間に噴火します…。仕事の中で心理士さんに、怒鳴ってしまいそうなとき、自分の感情ってどうやってコントロールしたらいいんですか?と聞いたことがあります。その心理士さん的には、
- 小さなお菓子を用意して、イラっとしたらお菓子を食べる
- 声が子どもに聞こえないように、寝室に行って枕を顔に押し付けて叫ぶ
- お風呂で鼻の下まで湯船に浸かり、叫ぶ
とおっしゃられていました。昔は回避する方法を知らずに、私はひたすら何もせずに怒りに耐えていたので、ものすごくしんどかったのですが、その話を聞いて以降、自分の逃げ道を作るようにして、
- 心理士さんがおっしゃられていたようにお菓子をつまむ
- ジュースやお酒を少しだけ飲む(お酒は飲みすぎると子どもの事故などに注意できなくなるので、アルコールが弱い人は注意が必要)
- トイレに入ってSNSを見る
- 片耳にイヤホンを付けて、音楽・ドラマ・映画などを流して気をそらす
- 例えば食事はひたすら冷凍食品に頼るなど、できるだけ自分がしなければいけない工程を省いて労力を減らしてイライラする原因を減らしていく
という感じでやり過ごしています。
こんな仕事をしていても、怒りが爆発しそうになることは普通にある
イライラした時に自分の爆発しそうな感情を抑えるようにしてはいるものの、じゃぁ自分が精神的に安定して育児できているのかというと、そうではありません。年に1回くらいは「ここでパーンと叩いたら、静かになるんだろうな」と想像するくらいの状況があったり、数か月に1回くらい、真顔で感情的に怒鳴らないように別室へ逃げて我慢したり、「もう疲れたなぁ…」と涙が出てくる時もあります。
もっと優しく女神みたいに声掛けしたい…と思うことはよくあって、寝かしつけが終わって子どもの寝顔を見ていると、感情的に対応してしまったりしているのをとても後悔します。いつも我慢してきているのに、その一回でその我慢が水の泡になるように感じていて、勿体ないなぁと思います。でも人間なのでイライラして当たり前ですし、いつも同じテンションで対応するのも無理です。できるだけ冷静を保てるようにいつも心掛けていますが、自分の感情をコントロールするのって、本当に労力が要るなぁといつも思っています。大学時代の友人で、本当にいつも安定した対応をしている方がいるのですが、とてもうらやましく思ってしまいます。
『ドイツ流 絶対に怒らない子育て』の本と、伊藤忠の『子どもの視点』は子どもの事がよくわかって、ちょっと意識が変わった
ある時、図書館でたまたま手に取ったこの『ドイツ流 絶対に怒らない子育て』という本が、育児をする上でとても参考になりました。子どもの成長段階の事や、どうして親と子どもがぶつかってしまうのかなどといったことが、わかりやすく書いてあり、子どもの気持ちを理解しやすい本になっています。
子どもの困りごとに関してはどの国でも同じなのだなと思えます。「子どもが親を困らせている」という表現をされることがありますが、実は違って、それは子どもの成長発達の段階で、こういう理由があるからそういう状況になっているといったようなことが色々書かれています。
子どもの成長段階を知らないと、なぜ子どもがそうするのかということがわからず、スムーズに子どもが物事を進めないことに関して怒ってしまったりするので、まずは子どもに関する理解が重要なんだなと、この本を読んでしみじみと感じました。結構ボリュームがあるので、すべて読むのには根気が必要かもしれないですが、とてもおススメの本になります。目次をパラパラ見て、自分がちょうど子どもとの関りで困っている箇所があれば、見てみるのもありかと思います。
また、子どもを理解するのに、実際に子どもから見た生活を実体験できる「子どもの視点」というのを伊藤忠が作っています。
「子どもの視点ラボ」という展示イベントをされていたり、東京に「子どもの視点カフェ」という子どもの視点の展示+カフェのスペースがある施設があります。

大人ではわからない、子どもにしかわからない苦悩を経験することで、子どもに対する理解が深まり、いつも怒って注意していたことも、「子どもはこうだから仕方ないよね。どうしたらうまくいくかな?」ということを一緒に考えることで、少し保護者の気持ちも落ち着くかなと思います。
昔と違って、今は核家族化になっている中で、昔とは違う子どもとの関り方を求められているので、今子育てをしてる保護者の方々は、どの年代でも大変かと思います。子どもの関り方に関しては、未就学児であれば保健センターがあり、就学以降であれば家庭児童相談の窓口が必ずどの市町村にもあるので、関わり方で困ることがあれば一度相談して客観的に見てもらうと、解決の糸口が見つかることもあります。
育児の中で一番大事なのは『保護者の体調』
日本人に多いと思うのですが、「親は子どものために我慢して当たり前」という考え方です。もちろん子どもを産んだ以上、保護者としての責任はあります。ただ、保護者自身が身体的に精神的にボロボロの状態で子どもと上手く関われるかというと、それは難しいことだと思います。子どもに対して献身的な姿は美徳のような感じで思われますが、その分の見返りを子どもに求めてしまったり、子どもやパートナーにイライラしやすくなってしまうこともあるので、保護者の体は定期的に自分で守る必要があります。自分を守るためには、自分の時間が必要になります。育児をしている中で、一人の時間を作るのは簡単なことではありません。ただ、保護者の一人の時間は必要なので、月に1回でもパートナーや実家の協力を得て一人の時間を作るか、自治体がしている一時預かりやベビーシッターの制度を利用したり、預ける料金が安いファミリーサポートなどを利用してみていただけたらと思います。
頑張っている保護者が褒められるタイミングは、なかなかないと思います。でも私たち保護者は「子どもを健やかに成長させる」のが目標で、とりあえず子どもにご飯を食べさせる、お風呂に入らせる、寝かせることができていれば、保護者の役割としては十分で、とても頑張っていると思います。「今日も子どもが生きている、私偉い。」というくらいの気持ちで、毎日自分を褒めながら過ごしていただけたらと思います。
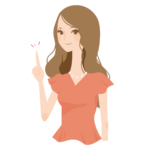
子育てのしんどさに関しては、こちらの記事も書いているので、よければ見てください。






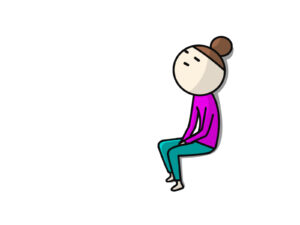



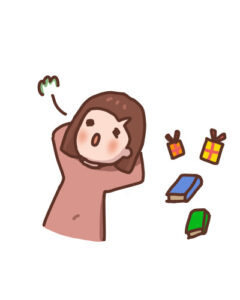


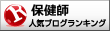
コメント